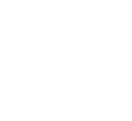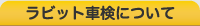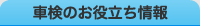トップページ > 車検のお役立ち情報 > 車検とは
車検の基礎知識
車検とは

誰もが一度は「車検」と言う言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか?そして、車を所有している場合に「車検」を受ける必要があるということは実際に車を保有している人はもちろん、車を保有していなくても知識として知っている方が多いと思います。では、この「車検」どのようなことを行うのでしょうか。
車検とはいわば車の人間ドックAbout automobile inspection
車検とは正式には「自動車検査登録制度」といい、検査によって安全に使用できる車であることを確認すると同時に、その車の所有権を公証する制度です。登録には一定期間ごとの更新が必要となり、3、5、7ナンバーといった自家用自動車と50ナンバーの自家用軽自動車であれば、初回が3年、2回目以降は2年ごとに行う必要があります。新車の場合は購入して3年目、5年目、7年目、9年目…に検査を受ける必要があるということになります。ご自身の車が車検を受けるタイミングがよく分からないという方はフロントガラスに貼ってある、ステッカーまたは車検証に記載がありますので、一度確認することをお薦めします。
一般的に日本国内での特殊自動車を除いた自動車や250cを超える自動二輪車に対して、その自動車・自動二輪車が安全面・公害面などおいて保安基準に適合しているかどうかを確認するために、一定の期間ごとに国土交通省で定められた検査を行います。また、自動車の所有権を公証するためにも行われ、自賠責保険の更新も義務付けられています。
ただし、「車検」とはあくまで検査した時の車両の状態が定められた基準に適合しているかどうか、といったことを検査するもので、その後の車両の安全性を保障、また、コンディションを整えるものではありません。整備工場などでおこなわれる整備が付属された車検の場合には、検査基準となる安全面・公害面を十分にチェックし、必要な場合には整備をしたうえで車検を行うようにしています。
そして、車検を受けなければ運行をしてはいけないということが法律で定められていますから、万が一車検の切れた車両を運転した場合は道路交通法の違反となり、処罰の対象となります。無車検運行での違反点数は6点となっており、これを行った場合には免許の停止、また、以前に免許停止の処分を受けている場合には免許の取り消しとなるので十分に注意しましょう。
もし車検が切れてしまったら、市区町村の役所で臨時運行許可証(仮ナンバー)を取得するか、車を積載できるキャリアカーで車検場に運搬するなどの対応が必要になります。

車検の種類

1995年に道路運送車両法の一部が改正され、「車検」が身近なものになりました。それまでは、実質的にディーラーか民間車検場に任せるしか選択肢はありませんでした。しかし、新車両法の導入による規制緩和でユーザー車検が身近になり、車検の際の選択肢が増えてきました。同時に過剰整備が多かった整備業界も整備代金の値下げや明瞭な料金体系の掲示など、自動車ユーザーにとっても嬉しい状況になってきました。ここでは、車検の種類についてご説明します。
ディーラー車検Dealer inspection
自社製品ならその知識量、技術力ともに他の車検工場や整備工場よりも圧倒的に信頼できる整備を行ってくれます。ディーラーの整備師達は、自社製品をメンテナンスするための専門の教育を受けています。しかし、他社製品の整備にはやや問題があります。
整備工場Maintenance shop
ディーラーと違い、取り扱い車種を限定していないので全てのメーカーに対する基本的な知識があるので、ほぼ全メーカーの整備が基本的には問題なく出来るのが特徴です。ただし、ディーラーのように最新の技術などに欠ける部分も。
車検専門チェーン店Specialty chain stores
車検を主要商品にしているので、整備工場よりも車検のノウハウは充実しています。また、車検に特化しているため、ディーラーよりも最新のシステムを導入している場合もあります。
ガソリンスタンドGas station
車検で預かった車は、各スタンドから提携している整備工場や自社の整備工場へ移動して車検を行います。
車検代行Inspection agency
代行車検には、整備はありません。つまり、車検で預かった車を陸運局に持っていき検査を行います。あくまでも車検という検査に合格させることに特化していますので、車検通過後にトラブルが起きた際にも保証はありません。
ユーザー車検User inspection
法律に基づいて自動車のユーザーが自ら点検し、国の検査場に車検を受けに行く事を指します。国の検査場で行う検査は、ブレーキテスターや排気ガステスタなどによる機器検査と目視検査を行い、検査の時点の安全面や公害面を検査するものです。車検後の車の安全性は全く保証されるものではありませんので、安全性の責任はユーザーが管理する必要があります。